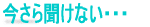  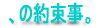 |
| |
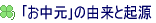 |
|
中国の道教の行事「三元(  )」(上元、中元、下元) の一つで贖罪の日でした。 )」(上元、中元、下元) の一つで贖罪の日でした。
これが日本に伝来して盂蘭盆(うらぼん)の行事と重なり、祖先の霊を供養、
両親に食べ物を贈る風習となり、これが目上の人、お世話になった方々に
贈り物をする「お中元」に変化したと言われています。
|
|
 |
|
「のし紙」は、紅白の5本(又は7本)の、
花結び(蝶結び)に熨斗が付いたお祝い用(  )を用います。 )を用います。
濃い色の墨の楷書体での表書が基本です。
献辞(上書き)は水引中央結び目の上に「御中元」と書き、
名前は水引中央結び目の下に献辞よりやや小さめに書きます。
日頃大変お世話になっている方々には贈り物に挨拶状を付けるか、
届く頃に手紙か葉書による挨拶状を送るようにする事をお薦めします。 |
|
 |
|
「どなたに、何時まで贈る?」は、明確な決まりはありません。
贈る方のお届け先さまへの気持ちであり、それぞれの考え方だと言えます。
仲人や媒酌人などの場合は一般的に最低3年間は必要とされています。
主治医や習い事の先生にはお世話になっている期間中は贈るケースが多いようですが、
幼稚園・学校などの先生、仕事の上司などはお届け先への配慮が必要な事があります。 |
|
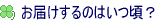 |
|
今年一年の前半の区切りのお届けなので、
6月下旬から8月上旬までの間に、お贈りすると良いでしょう。
時期は地方によって多少違いがありますので、注意が必要です、
関東地方は7月初旬から15日頃、関西以西は8月初旬から15日頃までと云われます。
お届けのタイミングを逃した時は「暑中御見舞」として贈ります。
関東では立秋をすぎると「残暑御見舞」とするのが一般的で、また、目上の方へは、
「暑中御見舞」「残暑御見舞」ではなく、「暑中御伺い」「残暑御伺い」とすると良いでしょう。
注:「暑中」とは二十四節気の中の「大暑」に当たる時期で、7月20日ごろから立秋の前日までのことを指します。 |
|
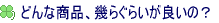 |
|
贈る側の心が相手に伝わり喜んで頂けるものが最高の品です。
高価であっても、お酒が飲めない方に酒類を贈っても喜ばれません。
先様の家族の年齢、人数、好みなどを知っておくと、より喜ばれる贈り物が出来ます。
商品の価格は、お世話になっている程度等で決めるのが一般的ですが、
昨年、2007年は3千円〜5千円の商品が多かったようです。 ( 2007年調べ →  ) ) |
|
 |
|
お世話になった方へのお贈りものなので、一般的にはお返しは不要ですが、
届いた後に出来るだけ速やかに電話か手紙でお礼の心を伝えると良いでしょう。
もち論、返礼として同額程度の品を贈ることは、特に問題はありません。 |
|
 |
|
お世話になっていることに対する感謝の気持ちであり、お祝いごとの贈り物ではないので、
贈り主、先方のどちらか(又は双方)が喪中のであっても、お中元を贈ることは問題ありません。
四十九日を過ぎていない場合や、まだ気落ちされていると感じる場合などは、
お届け時期をずらし、「暑中見舞」または「忌中御見舞」や無地のしで贈られるのも一案です。
なお、キリスト教には喪中という考えは無く、教徒間で贈り合う事は特に問題はありません。 |
|
|
|
|
|